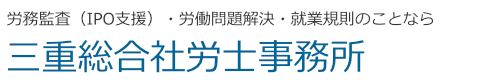高難度業務とは、特段、何か定義されているものではありません。
高難度業務とは、特段、何か定義されているものではありません。
独自に使用する呼称としています。
当事務所は、複数の研究会に参加し、日々、スキルアップと(小さなことでも)業務に繋がる情報のアップデートに努め、単純な問題解決は当然のこと、複雑・猥雑・様々な争点が絡み合う事案に対して、積極的に取り組み、相談者、顧問先の皆様の業務支援に徹して参ります。
| 高難度業務を定義付けすると・・・ (1)イレギュラー・ケース、定型業務ではない法的思考力、独自の法的スキームが必要な業務 (2)雛形では足りない書式・書類の創作が必要な業務 (3)これまでに前例のない業務 (4)問題解決に法律論、法的スキームだけでは足りない業務又は最終的に解決でないランディングが必要な業務 (5)企業法務、民事法務ともに刑事事件が関連する(可能性がある)業務 |
2.例えば・・・
例えば、軽いな問題として、退職代行サービスの対応についてです。
よく、退職代行サービスの方は、労働者との直接の連絡を取らないよう、連絡が必要な場合は退職代行サービスの窓口を経由してください、と言われます。この退職代行サービスが弁護士事務所であれば尚更、この様な内容を書面でも、口頭(電話)でも、伝えてきます。
この場合、過去には会社の経営者の中には「なぜ自分のところで雇用している従業員と話ができないのだ?!」と憤慨される社長もお見えになりましたし、企業の人事労務担当者の方は、頭を悩ませながらもそれに従っておりました。
果たして、この要請には法的拘束力はあるのでしょうか。
また、会社が退職届の提出を求めても、退職代行サービスは「法的には退職届の提出義務は無い」として、強く否定されるところもありました。
この場合、会社は退職届の提出を求めることはできないのでしょうか。
次に、状態としてある変形労働時間制を採用しているとの説明があり、就業規則、労使協定、雇用契約書、そして実務対応を確認してみると、労働基準法に定められている有効導入要件を満たしていないことが確認されました。しかし、長年、当該変形労働時間制を採用しているため、この考え方を変えてしまうと勤務時間、休日、そして残業代にかなりの影響を与えてしまうことが明白でした。
そこで、現在導入している変形労働時間制を有効に導入しているものとして運用するには無理があるとして、その運用を断念しなければならないのでしょうか。或いは、何か手立てがあるのでしょうか。
この場合のポイントは、制度趣旨・目的の定義付けと従業員代表者の選任手続を適正に行い、労使協議委員会や労働時間制設定協議委員会といった協議を行う会議体を設け、いかに適正運用につか付けることができるか、が一つの対応の仕方と考えます。
こういった内容の問題、つまり、ここでいう高難度業務を対応することが、当事務所の顧問サービスとなります。
3.セカンドオピニオン
 当事務所ば、他に顧問の社会保険労務士の方と契約をなされている企業からの御相談も受けております。
当事務所ば、他に顧問の社会保険労務士の方と契約をなされている企業からの御相談も受けております。
上場企業や大規模企業、中堅企業、中小企業、規模を問わず、当事務所に相談顧問としてのご依頼を多々頂いております。
何か問題が発生した場合、つまり高難度業務については、当職に意見を求めるケースや、当職が一緒になって対応するケース、対応は様々ですが、今も多く対応をしております。
現在、こういった依頼も多くなってきておりますので、手続き業務や給与計算業務を除いた高難度業務対応型顧問サービスのご依頼も承っておりますが、セカンドオピニオンとしての顧問契約も対応いたしております。
4.他事務所の顧問契約サービスが当事務所の高難度業務対応型顧問サービス
 高難度業務対応型顧問サービスのメリットは、通常では解決が難しい業務の対応にあると思いますが、それを解決するまでの過程、またはその後に、何らかの対策を講じるための提案をさせていただきます。
高難度業務対応型顧問サービスのメリットは、通常では解決が難しい業務の対応にあると思いますが、それを解決するまでの過程、またはその後に、何らかの対策を講じるための提案をさせていただきます。
それは、規則規程の変更、実務運用の見直し等々、その内容に即した提案をさせていただくことで、再発防止とともに、将来発生しうる問題へのリスクヘッジに繋げていきます。
また、社長や人事労務担当者の方が、一人で悩むことなく、解決へ向けて伴走いたしますので、皆様の不安の低減することになります。
5.サービスについて
高難度業務対応型顧問サービスは、他事務所でいう労務顧問契約のことです。
同じ顧問契約でも、当事務所の顧問契約は全て高難度業務対応型であり、所長の三重が全て担当させていただきます。
高難度業務対応型顧問サービスは別料金となります。
なお、高難度業務対応型顧問サービスと手続業務や給与計算業務等を一緒にご依頼いただく場合は、
費用についてはセット割を行っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
| ページトップへ戻る |